避けられた戦争:パーセプション・ギャップの積み重ねが平和を壊す
(この原稿は今年8月の終戦記念日にメルマガで発表されたものですが、
反響がおおきかったので、サイトでも発表することにしました。)
本日は終戦記念日にあたり、
緊急特集で小松啓一郎先生とのインタビュー記事を配信します。
歴史認識の問題がいかに深いか、
そして日本政府がこれまできちんと取り組んでこなかった慢心を思います。
太平洋戦争では310万人もの命が失われました。
その太平洋戦争に至るまでのギャップの積み重ねについて、
小松啓一郎博士に伺います。
<経歴>
政府系金融機関に10年間勤務(ニューヨークではウォール街で為替トレーダー)。
1990年オックスフォード大学政治経済学部に入学。
91年オックスフォード大学大学院に進級。同年、同大学で非常勤講師(「日本経済」担当)。
94年博士号取得(政治学・国際関係論)。
世界銀行・海外民間投資促進コンサルタント、英国通商産業省・上級貿易アドバイザー、
英国海外貿易総省・上級貿易アドバイザー等を歴任。
現在はマダガスカル共和国大統領特別顧問、英国王立国際問題研究所会員、英国国際戦略研究所会員、
地球環境平和財団・欧州中東アフリカ代表。
英国でコマツ・リサーチ・アンド・アドバイザリーを設立、代表に就任(2005年)。
——————————————————————————————————-
8月といえば「終戦とお盆」の月です。日本にとっては敗戦が決定し、
戦勝国にとっては冷戦が本格化した月でもあります。
戦争を避け、平和維持の努力を重ねていくことは国の義務でもあります。
それでは、じっさいにどういう努力の積み重ねが必要か?
これまでも日米開戦・太平洋戦争に至るまでの歴史研究が数多く積み上げられています。
今回は、小松啓一郎先生に、
御著書『暗号名はマジック:太平洋戦争が起こった本当の理由』
と『複眼思考:忍び寄る国際経済危機〜英国からの検証~』
に沿ってお話を伺います。
大井: 小松先生の御著書『暗号名はマジック』は
オックスフォード大学博士号論文(政治学・国際関係論)の日本語普及版です。
その帯には、「じつは日本もアメリカも戦う気はなかった!」と衝撃的な一文が付いています。
戦う気がなかったのに、日本と米国はどうして悲惨な戦争に突入したのでしょうか?
小松:一言で言うと「認識のズレ」、国際間の「パーセプション・ギャップ」です。
1941年12月8日のパールハーバー
(日本海軍航空隊が太平洋上のハワイ諸島でパールハーバーに停泊中の米艦隊を奇襲攻撃した軍事作戦)に先だち、
日米間では開戦回避を目指す二国間交渉が続けられていました。
その外交交渉中、東京の外務本省とワシントンD.C.の駐米日本大使館の間で
電文が頻繁に交わされており、
その内容は暗号化されていました。
しかし、じつはこの暗号メッセージがアメリカの陸軍と海軍の情報部で
傍受・解読されていました。ここまではわりと知られた事実です。
問題はその先です。
アメリカ側で密かに解読されたメッセージとは言っても、
それは日本語電文特有のカナ文(漢字無し・句読点無し)のままでしたから、
まず、それらを平文(漢字や句読点を補った通常文)に戻し、
そこから大統領や国務長官に報告するためにさらに英訳しなければなりません。
アメリカ軍の情報部では、こうした日本の外交暗号情報の解読・英訳された情報を
「マジック」という暗号名で呼んでいました。
しかし、暗号の解読作業こそ成功したものの、
平文への変換とその英訳作業の段階では数々の誤訳や曲訳
(辞書的・文法的には必ずしも「誤訳」したとまで言えなくても
原文の書き手の意図とは著しく違った曲解に基づく不正確な訳文)
が発生しており、それらが積み重なって結果的に重大な交渉決裂要因を作り上げていったのです。
大井: 小松先生は、その誤解・曲解の過程を歴史学の手法を用いて
学問的に検証されたのですが、
具体的にどのような誤訳があるのですか?
それは悪意に満ちた曲訳といえるのでしょうか?
そうであれば、暗号解読・情報部の責任になりますね。
小松: じっさい誰が翻訳官だったかについては公表されたこともなく、判然としていません。
また、必ずしも意図的な悪意のある誤訳・曲訳とまでは言えないケースが
圧倒的に多いと思います。
もともと、私の論文執筆の趣旨は責任者を突き止めることではなく、
あのような重大な誤訳・曲訳の連続という情報機関の失敗体験もまた、
不要な国際摩擦を少しでも減らしたいと願う世界の人々の貴重な教訓として共有することです。
大井: 具体的にはどのような誤訳・曲訳が致命傷となったのですか?
小松: 詳細は、オックスフォード大学と大英図書館に提出した博士号論文 の
出版バージョンである
“Origins of the Pacific War and the Importance of ‘Magic’” (Routledge,2009)をご覧下さい。
405頁から “List of Important ‘Magic’ Mistranslations, November1941”
(1941年11月中の「マジック」による重大な正・誤訳表)を提示してあります。
これは約8か月間にもおよぶ日米交渉中に頻繁に起こっていた誤訳・曲訳のうち、
特に1941年11月中の1カ月間の事例を抽出してみたリストです。
事例があまりにも多いため、あえて1カ月間分だけを一覧表にしてみたのです。
しかし、それでも、致命的と言っていいような誤訳・曲訳がいかに多いか、
ご覧になった方々は誰でも驚かれることと思います。
大井: 1941年11月というのは、ちょうど日米開戦前夜と言っていい時期ですね。
先生の日本語版の著書『暗号名はマジック』では、日米ともに「国益の方向に日米開戦はなかった」とあります。
小松: そうです。少し詳しい話になってしまいますが、そもそも、欧州方面では
1939年9月1日に始まったドイツ軍のポーランド侵攻をもって、
英仏中心の連合国陣営とドイツやイタリアを中心とする
枢軸国陣営のぶつかる第二次世界大戦の火蓋が切って落とされました。
しかし、日米両国はそれから2年以上も後のパールハーバーまで、
欧州戦線に関する限りは中立国のままでした。
たしかに、日米間にはそれ以前のいきさつから、かなり深刻な相互不信も醸成されていました。
しかし、中立時代のアメリカではフランクリン・ルーズベルト政権が
ナチス・ドイツとの正面衝突を「いずれ不可避」と予想していたため、
対日戦争のほうはできるかぎり回避したいと考えていました。
他方、日本側(特に陸軍)も過去数年間の日中戦争で疲弊していたうえ、
満洲国や日本本土の北辺周辺の正面防衛線で増強されてきた
ソ連軍の大兵力に脅威を感じており、
対米戦争まで考える余裕は無いというのが本音でした。
つまり、日米両国にとって太平洋方面とは「正面」というより「背後」だったため、
その「背後」での軍事衝突は回避したいと考える切実な事情があったのです。
この事実は日本の外務省や米国の国務省(外務省に該当)の資料のみならず、
当時の両国の軍部の資料を見ても明らかです。
たしかに、日米の海軍サークルでは潜在的な敵国(仮想敵国)同士と考えていましたが、
外交交渉の開始時点では本気で開戦する気だったわけではありません。
結局のところ、当時の両国はナチス・ドイツとソ連という別々の潜在的敵対国家の
存在を意識していたため、結果的に「衝突を避けたい」という点で日米の国益がむし
ろ一致していたのです。
だからこそ、開戦回避を目指す交渉が8か月間もの長きにわたって続けられたのでした。
日米ともに「国益の方向に開戦はなかった」と言うのはこういう意味です。
そうなると、ドイツを相手に苦戦中だったイギリスに味方して
参戦せざるを得ないと考えていたルーズベルト政権としては、
来たる米独開戦に際して、そのドイツと三国同盟(日独伊)まで結んでいる日本が
敵対的に対米参戦に踏み切る可能性があるかどうかも重大な関心事でした。
一方、日本がドイツとの同盟関係に踏み切った理由はあくまでも
ソ連からの本格的軍事攻撃の可能性に備えて東西
(ソ連の東側に位置する日本と西側に位置するドイツ)から挟み撃ちにする
防衛態勢を作ることであり、米国を敵国と見なしてのことではありませんでした。
したがって、日米間にはそれなりに開戦回避への「合意」の余地も残っていたわけです。
しかし、実際にはそれまでに醸成されていた相互不信の深さが
日米間で重大な誤解を積み重ねることになり、
それが決定的な誤訳まで繰り返し生んでしまう結果になったのでした。
誤訳の具体例をあげてみましょう。
1941年11月20日付けの来栖駐米大使宛電文(東京から発信)のケースでも、
米国側のマジック訳はその内容を決定的に誤って伝えてしまいました。
日本語原文では、三国同盟における日本の参戦義務について、
ドイツとは別の「自主的」な判断で行動し、
アメリカの対独参戦という事態に至っても
(ドイツ軍が先に米軍を攻撃したものと日本側が「自主的に判断」すれば)
対米戦争に自動的に参戦する義務はないということでした。
つまり、日米交渉で合意に達することができれば、
その後に米独戦争が勃発しても、
日本側としては同盟国ドイツに影響されずに自主的(独自)に判断することができ、
事実上は「参戦しない」との方針を伝えたかったのでした。
ところが、アメリカ側のマジック情報担当者は、三国同盟による日独関係を
日本が「自動的に(automatically)」参戦する義務を負っていると思い込んでいたため、
正しくは「independently」と訳すべき日本語の「自主的に」という部分を
「automatically」と完全誤訳してしまいました。
その翌11月21日には来栖大使がハル国務長官と会い、
日本の義務について電文どおりに説明したのですが、
すでに誤訳情報がアメリカの上層部に届けられていたため、
来栖大使の説明努力も無駄に終わってしまいました。
来栖大使本人から「independentlyに(自主的に)判断する」とわざわざ英語で
説明したにもかかわらず、ハル長官はそれを
「来栖個人の解釈だ」として「役に立たない」と退けてしまったのです。
また、日本側では三国同盟の調印当時に駐独大使だった来栖大使本人こそ
(当事者の一人として)日本の自動参戦義務がないことを
アメリカ側に説明する適任者だと判断していたのですが、
ナチス・ドイツを敵視していたハル長官のほうは、
まさにそのような経歴を持つ来栖大使だからこそ、かえって信用しなかったのです。
ハル長官のこの種の不信感は「誤訳ではないのか」との疑念を抱く
余地さえなくしてしまいました。
結局、アメリカの翻訳官たちの根強い不信感もあって
誤訳・曲訳だらけになっていたマジック情報なのですが、
それをハル長官もまた鵜呑みにしてしまう結果になったのです。
大井: 息が詰まるような展開ですね。
先生の著書で私が強烈な印象を受けた箇所は、「
米国は満州国という既成事実を承認しない旨のいわゆる『不承認政策』を発表したものの、
日本に満州国からの”撤退を要求した”という明確な自己認識がなかった」というくだりです。
にもかかわらず、日本側が”要求された”と感じていたという指摘(本文pp. 152-153)です。
日本では、米国側があえて撤退要求を文言にあらわさなかった戦略的意図を見過ごし、
実際以上の重圧を感じ、極度に緊張を持ち続け、
最後には、開戦不可避という状況判断となり、開戦決意というよりは開戦覚悟に至ってしまった。
こうした米国側の誤解や日本側のオーバーリアクションという現象は、
80年代の日米貿易摩擦や今のTPP交渉にも見られますが、
ずっと前からあったのですね。
小松: そうです。私には英国通商産業省に勤務していた経験もあるのですが、
その具体的な体験に基づく拙著『複眼思考』(2006年、ジェトロ)では、
日本と英国の二国間の経済・通商交渉の現場から日英間のパーセプション・ギャップを
検証してみました。
日本の場合は、自分の等身大のイメージをなかなか持てない国のように見えます。
たとえば、1980年代末頃には不動産バブルの急激な膨張で自らの経済を過大評価し、
バブル崩壊後の90年代になると今度はいきなり必要以上に暗い社会的ムードに陥って
しまった。
そこでは実情を遥かに越える悲観論が横行し、
その極端な悲観論がまた外国の政府や産業界の誤解を招き、
日本経済を実態以上に悪く感じさせる、内外の投資意欲まで
不必要に減退させていきました。
そして、2006年になると、今度は地下資源の価格高騰という新手のバブルに乗ってしまい、
再び過大な自己イメージを抱いていくことになります。
これでは国際社会における日本の立ち位置がよく見えませんから、
海外との間に横たわる誤解を乗り越えていくという段階にもなかなか行きつけません。
大井: こうした点を踏まえたうえで、先生は今の尖閣諸島の問題や
慰安婦のような歴史認識の問題について、どうお考えですか?
小松: 今の領土問題や戦争責任の問題もまた、まずは歴史上の事実がどうであったか、
きちんとした研究の積み重ねの上で客観的事実に基づいて
一貫した方法論をもって議論すべきことだと思います。
このように言ってしまうと余りにも当然のことのように聞こえるかもしれませんが、
少なくとも、今までの日本ではそれがほとんど出来ていなかったと思います。
日米関係や日英関係の分析をしていて、つくづく実感させられるのは、
日本に対する国際的な誤解を効果的に解消しつつ、
こちらの言い分を正確に理解してもらうには、
非常に時間のかかる地味な努力の積み重ねがどうしても必要だということです。
日本はこうした歴史研究の積み重ね、あるいはその成果に基づくキメ細かな説明をさぼってきました。
そのツケが今、いろいろな側面で回って来ています。
最近の日本では声高な方々が「こちらの考え方を外国にも伝えて来る」などと
一方的に自己主張しているケースが増えているように見えます。
しかし、地道な事実究明への努力や丁寧な説明の努力を省いてしまって、
いきなり自分たちの言い分だけを主張してみても、国際舞台では誰も聞いてくれなくなります。
相手国ではその「説明」の場に出て来てくれることさえなくなってしまうのです。
大井: 日本が世界に向けて自国の意見を発信しようとしても、その根拠となるような
各国との共有プラットフォームすらありません。
世界とのパーセプション・ギャップは拡大する一方にみえます。
小松: パーセプション・ギャップについての一例ですが、日本が尖閣諸島の問題を重視している
のと同じぐらいの度合いで中国側もまた尖閣問題に気を取られていると考えるのは大いに疑問です。
中国と言っても、その一部、つまり軍部の中でも特に極東地域の担当部署や
尖閣周辺海域の沿岸警備を担当する諸部署ではそうであるにしても、
中国政府の中枢部ではむしろ、昔で言う「西域」、つまり現在のイスラム圏が気になっています。
特に1990年代以降に大発展し始めた中国経済が今後もある程度の成長ペースを
維持しながら生き残っていこうとすれば、
明らかに中東やアフリカの資源と食料を確保していかなければなりません。
しかし、その地域には多くのイスラム教徒が住んでいます。
一方、中国の「西域」方面では独立回復への運動の絶えないチベットの政治問題のみならず、
新疆ウイグル自治区での治安問題もあります。
この新疆ウイグルに住むイスラム教徒の大半はトルコ系ウイグル人なのですが、
あの地域でも歴史的な独立運動が続いており、
中国軍と頻繁に衝突することで多数の死傷者を出しています。
このような状況の中、今年(2013年)1月にはさらに遥か西方に位置する
アルジェリアのイナメナスという所で大量人質事件が発生しました。
結局、10人もの日本人を含む多数の人質が亡くなってしまったのですが、
あの事件以降、北アフリカ地域のイスラム原理主義勢力は
新疆ウイグル自治区内で同じイスラム教徒との対立を深めている
中国への反発をあらわにしました。
特にその中でも有力な勢力が「アルジェリアで5万人もの中国人が働いている」
と警告したのは不気味であり、深刻な治安問題です。
極東海域で南北に細長く横たわっている日本とは違い、
中国という国家は東西に非常に長い領域を持っており、
その西端ではアフガニスタンと国境を接しています。
北京政府にとっての関心事はむしろ西に向いています。
このような国際事情を全く鑑みないでいると、日本はまたオーバーリアクションを繰り返すことになりそうです。
大井: 先生は文明論的な視点をお持ちです。
そして、月刊誌「正論」(9月号)では、
「ポリティカル・コレクトネス(宗教・民族・性別などに基づく差別・偏見を防
ごうという考え方)をまったく分析せずに言いたい放題言っていると日本の立場は悪くなるだけ」)(p. 115)と警鐘を鳴らしています。
日本は明治維新以来、アジア諸国の中で最も早く近代国家として経済発展を成し遂げました。
そのなかで、日本人が近代的自我をもった個人として世界に発信できる存在になれるのかどうか、
これは福沢諭吉以来、日本にとって大きな課題になっていると思います。
小松: 拙書のなかでは、相互の誤解とその結果としての重大な誤訳がなければ
日米間の太平洋戦争を「防げた」と書きました。
しかし、現実には、宗教や民族が異なれば、誤解・曲解が起こるのは避けられないと思います。
国際社会では、一方的に「日本が悪い」と主張される歴史認識問題や戦争責任問題が
すでにポリティカル・コレクトネスの一つとして定着しているとも言えます。
しかし、日本側からそれに訂正を加えながら説得力のある言い分を貫いていこうとするのであれば、
本当に地道な努力が必要となります。
拙著『暗号名はマジック』の元になった英文の博士号論文の学位審査時にも、
日本の旧敵国だった米英側では「それなら日本の軍部が悪かったのではなくて、
誤解・誤訳・曲訳に陥った米国側のほうが悪いと言うのか」と猛反発されました。
日本の国内では「日本だけが悪かったというのはおかしい」との鬱積した不満も
しばしば聞かれますが、旧連合国陣営の国々では
「もちろん、日本だけが悪かったのだ」、「その事実を直視せよ」
といった歴史認識が圧倒的だと感じられます。
私の場合、2人の面接官(オックスフォード大学の学内と学外から選ばれた専門家1人ずつ)を
含む16人もの審査委員会メンバーがいたのですが、
じつに数百項目にも及ぶ質問・批判を受けることになり、
1年間にもわたって論争を続けることになりました。
このような体験から、歴史問題をめぐる海外の目が日本に対して
如何に厳しいものであるかを強く実感させられました。
結局、日本語も含む各国語の第一次資料(原資料)を中心に
500ページ近い論文にさらに追記していくうち、
ついに試験官の間でも
「論旨が証明された」ということになり、学位授与に至りました。
これは「米英側の対日参戦の正当性は充分にあったはず」、
「そうでなければ、膨大な米英軍将兵の犠牲もまた、正当性の疑わしい戦争で犬死にしたことになってしまう」
との感情論や固定観念を英国のアカデミズムが越えようと葛藤した証でもあり、
つくづく、フェアな姿勢の現われと感じています。
大井: 英国では「タブーなき議論」を徹底するアカデミズムの伝統がしっかりしていて、
先生のような研究が積み重なって行く素地があります。
日本でもそうした客観的な研究が続けられるのかどうか、これから試されることかと思います。
本日は、有難うございました。
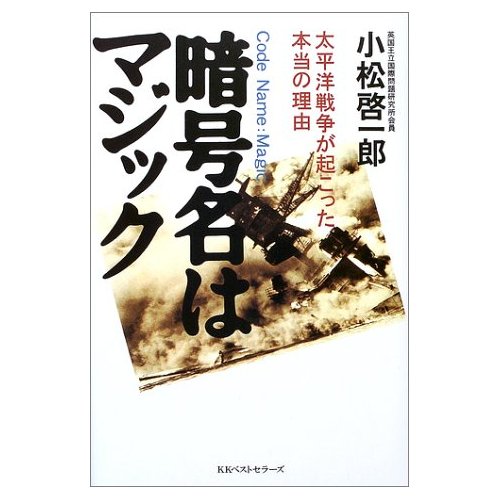


コメントは終了ですが、トラックバックピンポンは開いています。